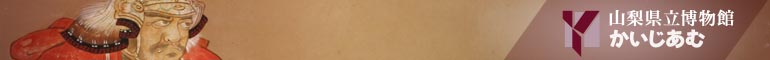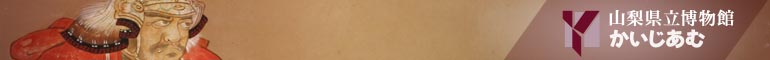山梨県立博物館では、毎年1回から2回民俗芸能の上演を行っています。
今回は、大月市笹子町に伝承される笹子追分人形芝居(ささごおいわけにんぎょうしばい)を上演していただけることになりました。
人形芝居(人形浄瑠璃)は、江戸時代に成立し全国的に盛んに行われた芸能のひとつです。山梨県内にも、かつて多くの人形芝居があったようですが、残念ながらその多くが明治時代に廃絶してしまったと思われます。そうしたなかで、今も伝承を続ける笹子追分人形は、大変貴重な存在といえるでしょう。
さて、人形浄瑠璃と聞くと、ちょっと難しそうだとかわかりにくそうと思われがちですが、そんなことはありません。かつては村人自身の手で上演され楽しまれてきた芸能ですから、意外にもわかりやすく親しみやすい内容です。博物館では、上演前に演目などの簡単な解説もいたしますので、初めての方もどうぞお気軽にお越しください。
◆日時 平成20年3月20日(祝) 午後2時から2時40分 ※終了しました
◆演目 傾城阿波鳴門(けいせいあわのなると)
寿三番叟(ことぶきさんばそう)
◆演者 笹子追分人形保存会(大月市笹子町)
◆場所 山梨県立博物館 ロビー ※申込み不要、参加無料
なお、当日は常設展で「右左口人形および頭と衣装」(県指定有形民俗文化財)を展示しています。あわせてご覧ください。(常設展の観覧料が必要です) |