|
■展示構成と展示資料
展示室は、導入展示と9つのテーマ、約50点の資料で構成されています。コーナーごとにシンボルカラーで区分けされており、展示資料に添えられたキャプションには「☆資料のひとコト」が書いてあります。資料についての「一言(ひとこと)での紹介」だったり、「ひとつの事柄(ことがら)」だったり。展示資料の魅力や意味、バックボーンとなる情報、あるいは展示を担当した学芸員のひとりごとだったりしますので、展示をより楽しみたい方や、説明を全文読むのが辛い方は、ぜひここからお楽しみください。
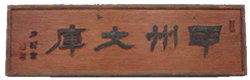
【展示資料】 |
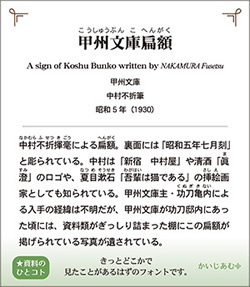
【キャプション】 |
※ヨゲンノトリ掲載資料(暴瀉病流行日記)は、常設展示室で展示しております。
|
導入展示(ニホンオオカミ) いのちの歴史との対話 文化のはじまり
山梨の宝 甲州文庫 絵画から見えてくるもの エア甲州道中旅行
近世甲斐国の書蹟 山梨流 災いの防ぎ方 危機のなかの山梨 毎日に微笑みを |
|
| ■ 導入展示 御坂のニホンオオカミ
|

【展示風景】 |

【ニホンオオカミ頭骨 ※ぼかしてあります】 |
ニホンオオカミは、明治時代の終わりごろ、生物学的な調査がされる前に絶滅したため、生きていた時の正確な姿すら、よくわかっていません。剥製は全世界に数点しかなく、本種を定義する基準となった標本(「タイプ標本」といいます)は、なんと日本ではなくオランダの国立自然史博物館が所有しています。これは、江戸時代に来日したドイツの医師・シーボルトが標本として収集したものです。
一方、ここに展示中の資料は、山梨県内の個人宅で代々保管されていたもので、関東の山間地域でみられた憑きもの落としの信仰と関係があると言われています。この2点の標本に対する取り扱い方の違いには、自然界のモノを全て記録しようとした西洋と、モノを通した精神的つながりを大切にしてきた日本の、自然に対する付き合い方の違いが表れているようにも思えます。
ニホンオオカミの例に限らず、日本が持つタイプ標本の質・量は、経済先進国のなかで自慢できるものではありません。一方で日本人は、新技術を取り入れつつ、コツコツと成果を積み上げていくことに定評があります。当館の資料は特に状態が良く、今後、ニホンオオカミの謎を解き明かすうえで大きな役割を果たすことになるでしょう。 |
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| かつては御坂の山々にもオオカミが棲んでいたのでしょうか。 |
ニホンオオカミ頭骨 |
|
|
| ■ いのちの歴史との対話―山梨県立博物館の自然史資料― |

【展示風景】 |

【フクロウ本剥製 ※ぼかしてあります】 |
山梨県立博物館では、太古の時代から現代まで、時代や種類にとらわれることなく、自然界に存在する資料を幅広く収集しています。ここでは、最近になって博物館に収められた資料をご紹介します。
自然史資料は「いのちの歴史」の証拠となるものであり、博物館は、それらを永久に保存し、将来にわたって多くの人が利用、活用できるようにしていく役割をもっています。一方で、自然史資料の多くはナマモノなので、そのまま放っておけば分解したり、壊れたりして、失われてしまいます。そこで大事になるのが標本づくりです。たとえば、鳥や獣の遺体は多くの場合、骨格標本や剥製標本にして保存します。頑丈にみえる化石資料も、修復や補強、あるいはレプリカ制作が必要になることは珍しくありません。また、様々な状態のナマモノを目の前にしての標本づくりは、往々にして時間との戦いになることが多く、その仕上がりには作り手の経験とセンスがはっきりと出ます。これが自然史資料の難しいところであり、おもしろいところでもあります。
机に向かって勉強するよりも、外で遊んだり工作したりするのが好きな人は、ひょっとすると自然史系の学芸員に向いているかもしれませんね。 |
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| この本剥製は、ホームセンターなどで手に入る材料を使って製作しました。 |
フクロウ本剥製 |
山梨の未来を拓くリニア工事で発見!
太古の山梨には海岸がありました。 |
リニア高川トンネル産出
新第三紀化石 |
|
|
| ■ 文化のはじまり―館蔵考古関係資料から― |

【展示風景】 |

【土偶 ※ぼかしてあります】 |
山梨県は縄文時代の遺跡が多く、特に今から約5000年前の縄文時代中期については、多彩な造形の土器や土偶などが見つかっており、全国的にも豊かな縄文文化が展開した「縄文王国」でありました。こうした文化は長野県にも共通し、両県にまたがる縄文時代の遺跡群は「星降る中部高地の縄文世界」として日本遺産にも認定されています。縄文遺跡や遺物は、この地における人々の文化が大きく華開いた「はじまり」を物語る貴重な文化財なのです。
また約1700年前の古墳時代の遺跡としては、甲斐銚子塚古墳など全国有数の規模を有する古墳があり、注目を集めています。古墳は早くから人々の目に止まり、地域の人々によって調査が行われることもありました。
山梨の県立施設では、考古資料の専門施設として山梨県立考古博物館がありますが、当館でも、県内の郷土研究者が調査・収集した資料や、遺跡・遺物に関する歴史資料などを収蔵しています。なかには、本県における考古学など学術研究の「はじまり」としての意義をもつものもあります。今回はそれらのなかから、縄文時代の資料、古墳時代の資料、平安時代の資料を紹介いたします。いずれも当時の人々の営みを知るうえで、また山梨の郷土研究の歴史をたどるうえでも、大変貴重な資料です。 |
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 戦後の食糧不足のため神社周辺を開墾した際に、たくさんの土器片が見つかったそうです。 |
深鉢型土器、釣手土器
(宮ノ前(七日子)遺跡 縄文時代中期) |
| 釈迦堂遺跡に代表されるように、甲府盆地東部は土偶の多い地域のひとつです。 |
土偶
(宮ノ前(七日子)遺跡 立石遺跡 縄文時代中期) |
| 周辺には「千塚」という地名が残り、古墳が多い地域だったことがわかります。 |
埴輪
(加牟那塚古墳 古墳時代) |
| 団栗塚は八代町域でも特に古い古墳と考えられています。 |
東八代郡八代村奴白の古墳発見記録 |
| 鏡の実物は現在確認できませんので、この拓本が貴重な資料となっています。 |
八代郡岡村銚子塚出土大鏡拓本 |
| 日下部遺跡は、現在の山梨市立山梨北中学校の敷地にあたります。 |
甲斐型土器 坏
(宮ノ前(七日子)遺跡 平安時代) |
| 大坪遺跡周辺は古代甲斐国府にも近く、重要施設が集まっていたと推定されます。 |
甲斐型土器 皿
(旧甲運村〈甲府市〉出土 平安時代) |
| 甲府盆地で生産された土器が、峠を越えて河口湖周辺にもたらされたものです。 |
「布ヵ」墨書土器
(旧長浜村〈富士河口湖町〉室沢出土 平安時代) |
|
|
| ■ 山梨の宝 甲州文庫 |

【展示風景】 |

【甲州文庫扁額 ※ぼかしてあります】 |
いまからおよそ70年前、郷土の歴史資料の宝庫そのものといえる「甲州文庫」が山梨県にやってきました。
「甲州文庫」は南アルプス市出身の功刀亀内氏が収集したもので、山梨県の社会・文学・政治・経済・人物など、あらゆるジャンルの歴史を知ることができる資料約2万点からなる資料群です。山梨県は戦争中の甲府空襲によって、千名以上の人命とともに、江戸時代以来積み重ねて来た多くの文化遺産を失っています。戦後まもなく功刀氏より譲渡を受けた甲州文庫は、失われてしまった山梨県の人々の地域らしさや心の拠り所を補ってくれた、まさに重要な「宝物」となったのです。
山梨県立博物館では、開館以来、常設展示や企画展、シンボル展などにおいて、「甲州文庫」を活用し、山梨県の豊かな歴史をお伝えしてまいりました。今回は改めて「甲州文庫」の重要性をご紹介するとともに、これまであまりお目にかけてこなかった資料をご紹介する機会とさせていただきました。常設展示室パート①(従来の展示室)では、どれが「甲州文庫」かな?、と探しながらご鑑賞いただくのも楽しいかもしれませんね。 |
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 甲州の約800の村々がびっちりと! |
懐宝甲斐国絵図 |
| 最後の100回目に突かれた札が一等賞高額当選になりまーす! |
富突き錐・木札 |
| 昭和26年の甲州文庫特別展示会にも「かなばん」から「こなから」まで展示されました。 |
甲州枡各種 |
| 私たちの時代の広告は、100年後、どのように思われるでしょう。 |
峡中広告集 |
| 山梨=水晶というイメージも全国的に根強く広まっています。 |
甲斐国水晶眼鏡 |
| きっとどこかで見たことがあるはずのフォントです。 |
甲州文庫扁額(中村不折筆) |
| 和装の元「モダンボーイ」 |
功刀亀内肖像写真 |
| 功刀氏は彫り物上手でもありました。「甲州文庫」印も自作かもしれませんね。 |
甲州文庫図書目録 |
| 功刀亀内と甲州文庫が激動の昭和前半をくぐり抜けて来た記録。 |
甲州文庫関係記事集帖 |
| 69年前に展示されたものも、今回の会場に展示されています。 |
甲州文庫移管関係綴 |
|
|
| ■ 絵画から見えてくるもの―大木家伝来の襖と浮世絵に見る厄災― |

【展示風景】 |

【菓子袋 ※ぼかしてあります】 |
山梨県立博物館は「冨嶽三十六景」を始め多くの絵画資料を収蔵していますが、今回はそのなかでも、見れば見るほど、制作された当時の姿に思いを馳せることのできる作品をご紹介します。
まずは甲府の豪商、大木家の資料のひとつ「高林古翠図」です。水墨に淡彩で表されたこの襖絵は、大木家で実際に仕切りとして使われていたことから、淡彩部分はわずかに色をとどめるに過ぎません。こうしたちょっとしたところから、長い間使われてきた歴史を感じることができるでしょう。
もうひとつは、厄災関連の浮世絵作品です。新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、その姿を拝めば難を逃れるという「ヨゲンノトリ」などがSNS上で拡散されていますが、江戸時代も疫病から逃れるため、「疱瘡絵」などさまざま浮世絵が作られました。また地震などの天災が起こった際、特に安政の大地震後に多く世に出された「鯰絵」などの風刺画は、当時の世情を大いに物語っています。
襖絵と浮世絵、性格の異なる資料ですが、どちらも往時の生活を垣間見ることができる、貴重な収蔵資料です。じっくりとご覧いただき、ぜひ当時の姿に思いを寄せてみてください。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 中丸精十郎 最大の文人画作品 |
高林古翠図 |
| 【前期展示】 7月27日(月曜)まで |
|
人気浮世絵師
お菓子屋さんのために菓子袋を描く |
菓子袋(升太の広告集 歌川国芳作) |
| ちゃんと薬で治そうね |
妙医甲斐徳本痳疹之来記 |
| さよなら!麻疹の神様 |
麻疹送出シの図 |
| 地震の後に大儲け |
流行職人尽 |
ちょいとそこのひげのお兄さん、
遊んでかない? |
治る御代 ひやかし鯰 |
| 【後期展示】 7月29日(水曜)から |
|
| 赤色の菓子袋を持ってお見舞いに行こう |
菓子袋(升太の広告集) |
| 金太郎の力で伝染病も吹き飛ぶ |
御菓子袋 |
| 地震に負けずみんなで乗り越えよう |
地震後野宿の圖 |
| 地震を起こした鯰、島流しになる |
鯰の流しもの |
| いろんな鯰絵、ご覧あれ! |
鯰絵 |
|
|
| ■ エア甲州道中旅行 |

【展示風景】(※写真の「甲州道中分間延絵図」は7月29日から展示箇所を変更しております。) |

【諸国道中商人鑑 ※ぼかしてあります】 |
新型コロナウイルスが人々におよぼした大きな影響のひとつに、「移動の制限」があげられます。海外旅行はもちろんのこと、県境をまたいだ移動も自粛され、「ステイホーム」が求められました。そんななかでも人々は、少しでも旅行やイベントの気分を味わおうと、ステイホームしながら、オンライン上でさまざまな画像・映像を楽しむ
「エア●●」が流行しています。
自粛は緩和されてきたけど、まだまだ思い切り旅行を楽しむような気分にもなれない…このコーナーはそんな皆様のために、博物館の展示で甲州旅行の気分を味わっていただく場として設けたものです。舞台は江戸時代の甲斐国の大動脈である甲州道中。五街道のひとつに数えられ、江戸日本橋から西へ進んで甲斐国に入り、上野原・大月・勝沼・甲府・韮崎などを経て信州下諏訪に至る、全長約210km、甲斐国内だけでも約100kmにおよぶ街道です。
まずは旅の下調べと準備から。旅程や旅先の名所・宿泊地を確認して、パスポート(通行手形)の申請も忘れずに。ガイドを頼りにさまざまな名所を見物しながら道中を歩き、旅の終わりに思い出を旅日記として残せば…、江戸時代の旅人たちも顔負けの「エア甲州道中旅行」をお楽しみください。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 階段のように示されるこの表の形は、現在も使われています。 |
東海道・中山道行程早見表 |
| 旅人が持ち運ぶのに邪魔にならないガイドブックです。 |
甲州道中細見記 |
| 宿や休憩場所の情報は、今も必須のチェックポイントですね。 |
諸国道中商人鑑 |
| 気になる旅の料金情報がわかるガイドブック |
甲州街道 |
| 民の旅の目的の多くは「社寺参詣」でした。 |
関所通行手形 |
| 甲府町方の役人が公務で旅行する際の行程です。 |
先触状 |
| 台ケ原は現在も宿場の風情が残る町のひとつです。 |
台ケ原宿絵図 |
| 江戸時代の最も精巧な道中絵図のひとつ |
甲州道中分間延絵図(写本) |
| 甲州のさまざまな名所が詳細に描かれています。 |
甲中遊記 |
| 名所だけでなく、甲州のさまざまな文物を描いた貴重な記録です。 |
並山日記(写本) |
|
|
| ■ 近世甲斐国の書蹟 |

【展示風景】 |

【並ぶ8点の書蹟 ※ぼかしてあります】 |
筆文字が書かれた掛け軸。こうした資料を書蹟(書跡)と呼びます。ここでご紹介しているのは、江戸時代の甲斐国ゆかりの著名人たちの書蹟です。
文字を目の前にすると、私たちはどうしても「何が書かれているのか」、「誰が書いたのか」、「どういう意味なのか」を気にしてしまいます。もちろんそれも大切なことですが、「どのように書かれたか」、つまり「書きぶり」を意識すると、奥深い書蹟の世界が見えてきます。
書蹟は、知人のお祝いなど、何かを記念して書かれることがあります。自作の詩や、過去の有名な作品の一部を書いて、他の誰でもない自分が贈ったもの、いわば自分の分身として渡します。書蹟を贈られた人は、書いてくれた人が筆をとっている姿を思い浮かべながら、その書蹟を見ているのです。
筆の運びを想像しながら、どのように書かれたのか、その勢いや柔らかさ、あるいは文字の並べ方など、「書きぶり」を想像してみましょう。次の一画に移るときに、筆を紙から離すのか、つけたままなのか、リズムはどうなのか、手を動かしながら想像してみましょう。内容や意味から離れて、文字そのものの「書きぶり」を味わえば、書蹟をより楽しく見ることができるでしょう。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 皇族らしい、線が細く、やわらかな筆さばき |
八宮良純法親王色紙 |
| 深呼吸して、気分すっきり! |
加賀美光章書蹟 |
| 勢いがあり、鑑賞性が高いすぐれた書蹟 |
志村天目書蹟 |
| 印鑑でおなじみの篆書体は最も古い漢字のかたち |
辻孔夷書蹟 |
| 70歳おめでとう! 長生きしてね |
小野通仙書蹟 |
| 花が咲き、月が照らし、思わず詩作にふけってしまう夜の情景 |
松井渙斎書蹟 |
| 一画一画が丁寧に書かれ、筆者の几帳面な性格がうかがえる |
乙骨耐軒書蹟 |
| くずし字のお手本のように整っていながら勢いのある書 |
浅野長祚書蹟 |
|
|
| ■ 山梨流 災いの防ぎ方 |

【展示風景】 |

【オコヤ ※ぼかしてあります】 |
山梨県内では、小正月を中心に道祖神祭りが行われています。道祖神は村境に祀られ、災いを塞ぎ止める神とされています。
道祖神には、厄病神と関連づける伝承があります。例えば、厄病神が道祖神を訪れ、厄を授ける人を記した帳面を預けていくという伝承は山梨県内でも見られ、祭りの時に帳面を飾る習俗も伝えられています。道祖神とともに疱瘡神(天然痘を流行させる神)を祀る例もあります。市川三郷町黒沢大木では石造物の疱瘡神を祀り、道祖神祭りではその神殿も作ります。道祖神と厄病神とは相反するようでありながら、実は強く結びついているのです。このような性格は、古くは11世紀の『本朝法華験記』に見られ、老人の道祖神が厄神に使役される存在として著されています。
このほか、祭りを止めると火事になる、災いを招くという伝承も見られます。道祖神は村を守るだけでなく、扱いによっては災厄を起こす厳しく恐ろしい一面も持つと考えられていたようです。
災厄をくい止めるために、山梨の人々は荒ぶる神を境界に祀り続けてきました。年中行事として受け継いできた先人たちの想いは、今の私たちだからこそ実感を持って受け止めることができるのではないでしょうか。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 村に災いが入らないのは、道祖神のおかげです。 |
山梨市市川地区のオコヤ |
| 道祖神祭りは続けなければなりません・・・! |
道祖神祭礼再開願 |
|
|
| ■ 危機のなかの山梨 |

【展示風景】 |

【疫病除守札 ※ぼかしてあります】 |
私たちは、新型コロナウイルスの感染拡大という危機を経験しつつありますが、よく参考とされる約100年前のスペイン風邪の際には、数次の流行の波がやってくるなかで山梨県民の約半数が罹患し、数千人の死者が出るという被害を受けました。
近代以前には、いまだ克服されていない結核をはじめ、天然痘、コレラ、赤痢などさまざまな感染症が社会の脅威となっており、山梨県には日本住血吸虫症(地方病)とのたたかいもあり、人々はたびたび広がる疾病に対して、常に立ち向かっていたのだといえるでしょう。疾病以外にも、自然豊かな山梨県には自然にまつわる災害も多く、近世以前には富士山の噴火があり、通史的には大きな水害がたびたび発生し、多くの生命財産が失われています。昭和41年(1966)の台風26号に関わる災害(死者・行方不明170名超)以後、山梨県では数十名以上が犠牲となる自然災害は発生しておらず、地域的な記憶や知見が薄らいでいることが危惧されます。
山梨県を襲った大きな地震は、嘉永7年(1854)の安政東海・南海地震までさかのぼります。災害と対応する人々の記録は、私たちが直面したときに頼りとなる有用なデータとなります。危機のなかの山梨で、どのような取り組みがあったのか、みなさんのお住まいの地域に引き付けて考えてみてはいかがでしょうか。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
| 甲府盆地の南西方向に被害が集中して起きています。 |
甲府大地震之記 |
| 甲州の古い地震の記録を載せた、数少ない貴重な資料です。 |
歳云録 |
| 常設展示パート1の「共生する社会」に関連する映像があります。 |
(昭和41年)26号台風災害記録アルバム |
| 大変な脅威が近づいているとき、心にも効く処方箋が必要です。 |
疫病除守札 |
| ヨゲンノトリが出現したとされるのもこのコレラの流行時です。 |
此節流行病救法 |
| 100年後には貴重な資料になっているかもしれません。 |
政府配付の布製マスク |
| 山梨にも感染症に長く取り組んできた歴史と努力の積み重ねがあります。 |
死体解剖御願 |
|
|
| ■ 毎日に微笑みを |

【展示風景】 |

【観音菩薩立像 ※ぼかしてあります】 |
昔から、疫病などのさまざまな災厄により、人々は繰り返し苦しめられてきました。現在のように科学的に物事が考えられていなかった時代、人々が救いを求めたのは信仰でした。病の流行に救いを求め、日照りが続けば雨を乞う。その祈りの先にあったのは神仏であり、なかでも観音菩薩はこの世でのさまざまな災厄を除くものとして、とりわけ多くの信仰を集めてきました。仏・菩薩に性別は無いとされますが、観音菩薩は優しい女性のような姿に作られることが多く、何より穏やかに笑みを浮かべたような表情は、拝む者の心を落ち着かせ、たとえどんなに困難な状況でも最善を尽くそうという、前向きな気持ちを励まし続けてきたのかもしれません。
ここ数か月、新型コロナウイルス感染症のために、外出を自粛するなど気分がふさぎがちな生活を送っておられる方も多いでしょう。そのような時でも、目の前にある仏の表情はどこまでも優しく穏やかです。現代において、科学技術は私たちをあるゆる面でサポートしてくれるようになりました。しかし私たちの心は、現代においても昔と変わらず、優しい菩薩の微笑みにこそ救われているのかもしれません。
|
|
| ☆資料のひとコト |
資料名 |
この像は1本の桜の木からできている。
素材まで気持ちを明るくしてくれる。 |
観音菩薩立像 |
|
| |
|
|
■関連イベント
※現段階で関連イベントの開催予定はありません。 |
|
■リーフレット・展示資料目録
・かいじあむ+(ぷらす)展示解説リーフレット(PDF:10.2MB)
・かいじあむ+(ぷらす)展示資料目録(PDF:0.3MB)
・かいじあむ+(ぷらす)展示解説テキスト版(PDF:2.4MB) |
|
|

